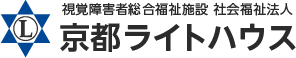第9回 会社員・吉川典雄(よしかわ のりお)
公開
優しい会社?
それは5年前の夏だった。およそ3ヶ月の業務からの離脱の後、人事部の調整を受けて、私は新しい職場で仕事に復帰した。緑内障が進行し、生来の高度近視と相まって視力が衰弱し、それまでの事業部の管理職という激務に耐えられないと観念したからだった。幸い、転属した職場は、以前に経験のあった知的財産管理についての本社機能部門。京都ライトハウスや京都府視覚障害者協会(京視協)の親身のご支援を受け、PCスクリーンリーダや拡大読書器を導入すれば、視覚障害者にもできる仕事があることを人事部に説得してのことだった。
私が勤める会社は、オムロン株式会社A)。今年創業80周年を迎えた主として制御機器を扱う電機メーカだ。創業者・立石一真の先見性によって、高度成長期にオートメーションの時流に乗り発展を遂げた。経営理念に「企業の公器性」をうたい、70年代、当時としては画期的な福祉工場「オムロン太陽」B)を設立し、障害者雇用を率先した。年間行事である全社員対象の人権研修では、「ダイバーシティと企業理念」のテーマでディスカッションがされるなど、人間尊重の職場風土の醸成にも力点が置かれている。
そんな企業だからこそ、中途障害者としての私の受容れも、粛々と進められた。私は恵まれている。確かにそうなのだろう。でも、不安と焦燥にかられて新しい職場に出勤した日、先輩から掛けられた一言は、私の心を一層乱した。「オムロンって、優しい会社だよね」。
はたして仕事を続けられるのか
オムロンという障害者福祉に理解のある会社にとってさえ、視覚障害者、それも中途障害者となれば、仕事のイメージが持ちづらいというのが、正直なところだろう。そのような者でさえ、とりあえず何ができるか受容れる。「優しい会社」とは、そんな慈悲深い会社という意味なのだろうか。「会社に甘えるわけじゃないけれど」と、後ろめたさが無かったといえば嘘になる。でも、それでも会社のために何かできるはずだと、ジレンマと組み合う日々が続いた。
会社員が障害を抱えることになったとき、本人の意思としては「辞めたくない/辞めたい」、会社の意思としては「辞めなくてもいい/辞めてほしい」ということによって、類型化されることだろう。それは、障害の程度、年齢、家族の状況、会社の状況、職掌など、様々な要因が絡み合って決まる。しかし、どのケースであっても、中途障害者はジレンマに陥る(図1)。それがトラウマとなって、濃淡はあるにせよ、その後の障害者の人生に影を落とすことになるのだ。
はたして仕事を続けられるのか。今の仕事を続けるか、新たな仕事人生を始めるか、判断は常に迫られ、下す結論は人それぞれだ。模範解答など、ありようがない。私のケースでも、年々衰える視力を補うための訓練と格闘しながら、その自問自答は5年経った今も続いている。
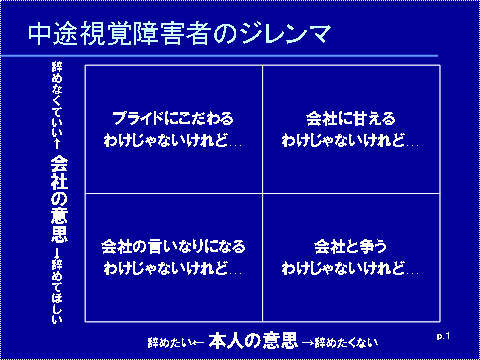
図1 中途視覚障害者のジレンマ
娘からの贈り物
私が仕事に復帰した頃、娘はまだ小学生だった。ある日、彼女は一冊の文庫本を差し出し、私に読んでみろと促した。当時既に私は文字がほとんど読めなかったが、邪気の無い奨めにしたがって音声図書でその本を「読む」ことにした。その本とは、サン=テグジュペリの『星の王子さま』C)。私が中学生の頃、著者の素朴な挿絵が印象的なこの本を、英語訳のテキストとして読んだことはあった。でも、その内容といえば、和訳にばかり懸命で何も残っていないというありさまだった。この童話とも寓話とも短編小説とも、あるいは時として哲学書ともいわれる作品を読み進めるなかで、私は衝撃的な一節に出くわした。それは、キツネが王子さまとの別れに知恵を授ける場面。「大切なものは、目には見えない」。
もちろん、これはフィジカルな視力の問題ではないことは明らかだ。しかし、著者の意図がどこにあろうが、この言葉は、三十数年の時を超えて、新たな啓示的な含意を伴いながら私に降臨した。大袈裟だと言われるだろうか。でも、人は人生で言霊ともいえるものに震撼し、畏怖する瞬間が一度はあるものだ。娘が意図したのかどうか定かではないが、彼女からの贈り物は、障害を抱えることになり、悶々とした日々を過ごしていた私にとって、まさに一条の光であった。
以来、私は視力に由来する絶望感に苛まれる度に、その命題の対偶を心のなかで繰り返す。「目に見えるものに、大したものなどない」のだと。
花の種のつながり
憤怒、怨嗟、羨望…。津波のように非周期的に襲来する負の激情にも、自ら平常心に収める術を少しは学んでいった。ぎこちない職場での立ち居振る舞いも、役割を見出すにつれ、次第に自然なものになっていった。周囲も必要なサポートを必要なときにしてくれる、ある種の「慣れ」が形成されていったように思う。
そのようななか、昨年の春、私の職場は部門ごと京都駅近傍から京阪奈に移動し、自宅の太秦からJR・近鉄・バスを乗り継いで、片道2時間近い通勤となった。新たな試練である。私は京視協にお願いし、駅での乗り換えのための歩行訓練を受け、なんとか独りで通勤できるところまでになった。事業所の最寄り駅周辺では、会社の仲間たちも手を引いてくれる。それでも朝夕の京都駅での通勤ラッシュは凄まじく、何度か白杖を折られた。
しかし、不思議なものである。通勤の途上、見知らぬ人たちが私に声を掛け、手を差し伸べてくれ始めた。私はふと思いつき、その人たちに感謝の言葉を添えた花の種の袋を手渡すようにした。それ以降、その人たちは、通勤で私を見かけるたびに、繰り返し声を掛けてくれるようになった。花の種のつながりともいうべきか、今では、その人たちとのおしゃべりも通勤の楽しみになっている。
不幸せの数と幸せの数
以前はよく、「失くしたもの」を数えていた。
例えば、アイコンタクト。目はものを見るだけではない。人は相手に自分がどこを見ているかを伝えることで、コミュニケーションをとっている。「白目」を進化させたのもそのためだ。「目は口ほどにものを言う」のだ。私はそのアイコンタクトによる意思や感情の伝達手段を失った。
また、例えば、スイートメモリーズ。震災などで家を失くした人たちが、口を揃えて言うことがある。「失くした家は建て直せるけれど、思い出の写真や手紙は戻ってこない」と。まさにその状況と同じだ。人には絶対見せられない自分だけの記念の品。私は手元にあっても見ることのできない、そんなスイートメモリーズを失った。
そして、若いときからのいくつかの趣味。絵画、囲碁、サイクリング…。
私は昨年から始めた社内での「視覚障害者の手引きセミナ」で、「失ったもの」の話をした。そのとき、ある受講者が示唆的な質問をしてくれた。「失くしたものはあるけれど、得られたものもあるのではないですか」。不意をつかれはしたが、私はしばし考慮して答えることができた。それは、「人の善意、人との絆」だと。
多くの人に助けられた。もし、障害者にならなかったとしたら、私は世の中にこれほどの無私の善意や利他の絆があふれていることに気づかずにいたにちがいない。不幸せも幸せも、「ほくろ」のようなものだという。どれも、「数えれば増える」。「失くしたもの」にもう恋々とすまい。人生にとって、かけがえのない「得られたもの」があるのだから。
触覚で拡がる世界
一方で、見えない世界を取り戻す、ささやかなチャレンジを始めている。
そのひとつは、囲碁。昨夏、手で触ってわかる碁盤と碁石を使った視覚障害者のための囲碁会が行われていることをテレビで知ったD)。京都ライトハウスでも、船岡寮のクラブとして行われているという。囲碁は下手ながら子とものころから親しんできた趣味。それがまた楽しめるかもしれない。しかし、クラブは平日に行われているため、仕事がある私には参加できない。そこで、関係者のご支援を得て、別に土曜日のサークルを立ち上げることにしたE)。視覚障害者に限らず、囲碁を始めてみようという人たちが気軽にきていただけるユニバーサルな囲碁サークルに育てて生きたいと思う(図2)。
もうひとつは、点字。これまで、視覚障害者でありながら、点字というものを心理的に遠ざけていた。情報機器の発達によって、点字によらなくとも情報の送受が可能なのだと、自分に見え透いた言い訳をしていたのかもしれない。触覚によって文字を読む、そのハードルの高さに、できるなら避けて通りたいという思考停止状態にあったのだ。しかし、何がきったけだったのかはわからない。今春、点字に関ってみようと思い立ち、京視協に無理をお願いし、土曜日の講習を始めていただいた。それがなぜなのか、うまく説明できない。でも、自分のなかで何かが変わり始めているのを感じる、ゆっくりとだが確実に。
視覚域を触覚域に、脳はクロスモーダル可塑性を持ち、失われた感覚を補うことができるというF)。その科学的研究成果は、私に凛々たる勇気を与えてくれる。ユニバーサル囲碁や点字など、積極的に触覚への関りを深め、新鮮な感覚の世界を拡げていきたい。

図2 「囲碁サークル 花ノ坊」にて
もう一度、風を切って走りたい
これも今春のことだが、私は市民ボランティアグループ「ユニーズ京都」G)に参加し、入洛する視覚障害者向けの散策などのイベント企画に関るようになった。私にはひとつの思いがあった。これまでイベントで体験していたタンデム自転車(二人乗り自転車)を、いつでも京都のサイクリングロードで走らせることはできないものかということだ(図3)。
京都には、「八幡木津自転車道線」H)という、嵐山から桂川・木津川を経て、奈良・飛鳥につながる立派なサイクリングロードが整備されている。しかし、今の京都府道路交通規則では、タンデム自転車のサイクリングロード(自転車歩行者専用道路)での通行が許可されていない。視覚障害者をはじめとする一人では自転車に乗れない人たちも、一般の自転車愛好家とともに京都でサイクリングを楽しめるようにするために、規則の改正を求める。私たちユニーズ京都は、京都サイクリング協会(KCA)I)とともに、今夏、京都府警と京都府ならびに京都市に「京都府のサイクリングロードにおけるタンデム自転車の通行に関する要望書」を提出した。
「もう一度、風を切って走りたい」。懸命にペダルを踏んで坂道を上り、ようやくダウンヒルにさしかかったときの爽快感は忘れられない。そんなサイクリングへの思いが発端だった。単なる個人の「願望」から「行動」としての第一歩を踏み出せたことは、私にとって大きな自信となった。これも、ユニーズやKCAという、すばらしい人たちとの出会いがあったればこそ。今後、要望書趣旨の実現に向けて、イベントの開催や賛同者への呼びかけなどを通じ、行政への働きかけを進めていきたい。

図3 タンデム自転車体験会にて
以上のとおり、私の今は表題の『かがやく…』とは程遠く、暗闇の向こうから差し込む一条の光をつや消しのビーズのように鈍く乱反射させているにすぎない。「障害を乗り越えていきいきと」という典型に同定されることへのささやかな抵抗が、このコラムをもしも屈託あるものにしたなら、これもある種の「ダイバーシティ」の発現なのかと、どうかご容赦いただきたい。
注釈
- A) オムロン株式会社:
- B) オムロン太陽株式会社
- C) アントワーヌ・サン=テグジュペリ著, 内藤濯訳 『星の王子さま』 (岩波書店, 2000年)
- D) 日本視覚障害囲碁普及会
- E) 囲碁サークル 花ノ坊
- F) ローレンス. D・ローゼンブラム著, 齋藤慎子訳 『最新脳科学でわかった五感の驚異』 (講談社, 2011年)
- G) ユニーズ京都
- H) 八幡木津自転車道線
- I) 京都サイクリング協会(KCA)
私のプロフィール
吉川 典雄 (よしかわ のりお)
1959年、京都市生まれ
京都市右京区太秦在住
1982年、立石電機(現・オムロン)株式会社入社
以来、製造業向け制御装置の開発に従事
2008年、緑内障と高度近視により視覚障害となる
現在は知的財産関連業務に従事
趣味は、川柳、読書(音声図書)、囲碁(視覚障害者用ミニ九路盤)
「囲碁サークル 花ノ坊」世話役
「市民ボランティアグループ ユニーズ京都」会員